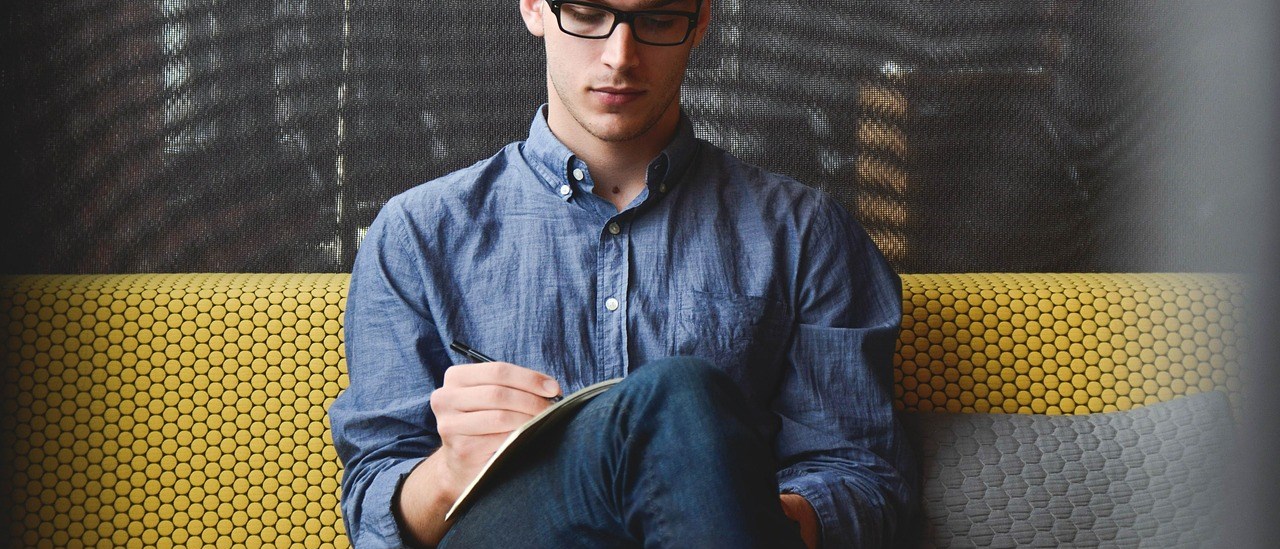本ページでは、ニュースレターの文字情報だけを掲載しております。
また、ニュースレターに掲載されているイベント情報は、本サイトの最新情報からご確認ください。
Be Social
私たちが暮らす地域や社会の事を他人事ではなく自分事にする。
そういった“ソーシャルな生き方”の魅力をお伝えします。
第37回 伊木知子さん
「子どもたちが育ち合う環境を地域につくる」
パンサー少年団 保護者代表
吹田市生まれの3児の母。
2016年、かつて一緒に活動していた仲間が継続する少年団※に、当時小学4年生の長女と参加し、現在に至る。
※小~中学生までの子どもたちが、自分たちで考えた遊びや行事を行う全国的な地域活動。
高校生以上の青年指導員が活動をサポートしている。
団で育った子ども時代
両親は共働きでしたが、寂しく感じることはありませんでした。
それは、小学1年生のときに入った少年団があったからだと思います。
学区も年齢も異なる仲間と遊んだり、合宿に行ったり、とにかく楽しかったです。
中学生になると、団の運営に関わることから、当時は「なんでこんな会議ばっかりやるんやろ?」と思ったこともありました。
子どもが主人公の団運営
団の運営は、中学生以上の子どもが中心となります。
異なる意見や少数の声にも耳を傾け、話し合いを重ねながら、みんなで調整し、前に進んでいく。
そんなやり方を、会議を通して少しずつ身につけていったように感じています。
合意形成の難しさと、その大切さを実感したこの経験は、今の私自身の土台になっています。
そんなこともあって、自分の子どもにも、同じような経験をしてほしいと思うようになりました。
保護者の立場になって
子どもたちは、「あんな中学生になりたい」「高校生ってすごい」と憧れの存在として見て育ちます。
そして、自分たちが団のお兄さんやお姉さんからしてもらったことを、自分より年下の子に自然としてあげるようになるんです。
保護者として関わる中で、ついつい口を出したくなりますが、自然と〝育ち合い〟が起きているこの活動をそっと見守りながら、バトンを繋いでいきたいです。
ここに注目!ラコルタの特集
地域で活動する学生たち
~自分たちの活動って「ボランティア」?~
座談会
近年、地域社会の課題解決に向けて多様な市民公益活動が展開される中、若い世代の関わりはその未来を担う重要な可能性として注目されています。
『全国学生1万人アンケート~ボランティアに関する意識調査2023~』(日本財団)で「過去1年間にボランティア活動を行ったことがない」と答えたのは75.3%ですが、そのうち57.5%がボランティア活動への参加を希望しています。
2017年調査結果と比較しても大きな差異はなく、コロナ禍以前の水準まで、ボランティア活動への参加意欲が高まってきました。
そんな中、地域では独自の団体を立ち上げて、ボランティアや市民公益活動を主体的に行っている学生がいます。
本特集では、吹田市・豊中市を中心に活動をしている学生3人に対談をお願いしました。
お話を伺うと、活動内容はもちろん、背景やきっかけも様々な一方で、共通点も見えてきました。
「ボランティアや市民公益活動に関心はあるが、まだ一歩が踏み出せてない」若い世代にとって、少しでもヒントになれば幸いです。
チーム竹未来
代表 吉田紗弥さん
追手門学院大学 地域創造学部 1年生
2023年4月立ち上げ。
高校生~シニアまで幅広い世代のメンバー6人が個性を活かしながら活動している。
#千里の竹の魅力発信
#循環利用
#共創
FASHLOOP(ファッショループ)
代表 三浦竜希さん
大阪大学 経済学部 3年生
古着回収活動やフリマを通じてみんなのファッションを循環させるため、2025年4月に立ち上げたサークル。
#服と人のつながり
#古着
#フリマ
にこれる
代表 辻 翔吾さん
大阪公立 大学大学院 農学研究科 2年生
2022年立ち上げ。
学習支援と子ども食堂を高校生~大学院生のスタッフが約50人で運営している。
#ご飯を食べにこれる
#学びにこれる
#遊びにこれる
活動していること
吉田:千里に多い竹を使って、竹あかりのワークショップを行ったり、キャンドルイベントで展示したり、廃材竹チップで植物を育て、植物発電実験をしたり…やってることが多すぎてうまく説明できないです(笑)。
Instagramで全部発信してるので、見てもらえたら嬉しいです。
三浦:古着のフリーマーケットサークルです。
万博記念公園等のイベントに出店してるんですが、もっと地域の人たちと一緒にやりたいと思ったんです。
今準備を進めてるんですが、ラコルタに古着の回収ボックスを設置して、その古着の販売収益を吹田市の「みんなで支えるまちづくり基金」に寄附するという活動を始めようと思ってます。
辻:小学生から高校生の学習支援と、勉強の合間に一緒にご飯を食べる子ども食堂をやっています。
月水金の週3回やっていて、子どもたちは毎回10~15人ぐらい来てくれてますね。
きっかけは?
辻:大学生になったら、何かしら 「意味あること」をしたいなと思っていたんですが、ちょうどその時、アルバイト先の塾の先輩が社会人の方と一緒に学習支援の団体を立ち上げるって話が出て、自分も一緒にやり始めたのが最初です。
そこから色々あって、学生のメンバーだけで学習支援や子ども食堂をやりたいという話になり、2022年に「にこれる」を立ち上げました。
三浦:サークル自体は、古着好きのメンバーで立ち上げただけなんです。
そこに地域とのつながりをつくりたいと思ったのは、大学の講義がきっかけですね。
箕面、豊中、吹田の市民公益活動センターを通じて地域の活動を学んだんですが「こんな面白い活動があるなんて全然知らなかった」って思ったんです。
「にこれる」のことも、その時知って「学生だけでやってるなんてすごい!」って思いました。
講義が終わった後、自分も何かやってみたくなって、自分が好きなことや得意なことで何かできないかなとラコルタに相談しました。
そこから地域の人たちとイベントで関わるようになってやりがいや楽しさを感じたんです。
吉田:「チーム竹未来」は、千里中央で行われたワークショップがきっかけです。そこで一緒になったグループの人たちで立ち上げました。
ただ、今思うと地域での活動の一番最初の出会いは、住んでるマンションですね。
すごく積極的に開かれているコミュニティという感じで、防災とかいろんなイベントでマンション内の人たちが繋がっていたり、お祭りで地域の人と繋がっていたり、いつもすごく盛り上がっていました。
物心ついた時から、それが当たり前だったので、ボランティアとか地域での活動は身近でしたね。
だから団体立ち上げるのも、「やってみるか~!」みたいな感じでした。
活動を続けてる理由は?
三浦:正直に言うと、授業を受けるまではボランティア活動は、地域に貢献したいとか、高尚な精神の人がやるもんだと思ってて、僕は違うかなと敬遠してました。
でも今は古着とか自分の趣味を発展させて、いろんな人を巻き込んでく手段みたいなところがあると思ってます。
吉田:竹あかりのワークショップを続けてるんですが、小学生からシニアの方まで、いろんな世代の人とつながれるのが大きいですね。
活動続けていると「見たことある!」「頑張ってね!」って言ってもらえるのも嬉しいです。
あとは企業の方から連絡いただいたりするのも、こうやって活動してるからかなって思います。
辻:最初の頃は子どもたちが来ても1人という日があって、金銭的にも余裕はなかったです。
そこから学生スタッフたちで話し合いながら、学校にチラシを配ったり、Instagramやってみたり、色々やったんですよね。
でもあんまり効果がなくて、来てくれた子たちの口コミで少しずつ増えてきました。
逆に今はスタッフが足らなくなって、どうやって増やすかを話し合いながらやっていて・・・。
そういう試行錯誤を、自分たち学生スタッフ主体でやっていることが楽しいから続けているのかもしれません。
自分たちの活動って「ボランティア」?
吉田:結構聞かれるんですけど、ボランティアっていう言葉だけだと違和感というか伝わりきらない気がします。
みんなが思うボランティアって災害支援とかごみ拾いとかそういうイメージが多いけど、自分たちはやりたいことをやっているという感じなので。
辻:たしかに団体のことを説明するときはボランティアって説明しますけど、奉仕的な精神でやっているのではなく、楽しくやっているだけですからね。
三浦:全く同意見で、自分がやりたいことを実現するための手段の一つが、たまたまボランティアだったという感覚なんで、ボランティア活動と言われるとちょっと違和感あります。
趣味に地域が掛け算されている感じなので。
同年代へ伝えたいこと
吉田:まずはやってみて欲しいです!
実際にやってみて、合わなかったらやめたらいいし、面白いって思ったら、またやってみればいいと思うので。
やる前にブレーキをかけるのはもったいないと思います。
やってみないと分からないことも多いですしね。
三浦:ボランティアって考えるとハードルが高いと思います。
自分も昔はそうでした。
一方で、やってみたいことっていうのは、みんなあると思うんです。
それを実現するための手段の一つとして、ボランティアとか地域活動もあるので、そうやって考えてみてほしいですね。
辻:僕はおふたりみたいに、いろんなことやりたいってタイプじゃないんですよ。
代表も自分から「やります!」って言ったんじゃなくて、活動続けてたら、いつの間にか代表になってた感じなので。
ただ、僕みたいに積極的じゃないタイプでも楽しくやれるところですし、いろんな人がいるんで、「自分にはできないかも」って決めつけないでほしいですね。
やってみたら、意外と楽しかったりすることの方が多いと思うので、そういう意味でも1回やってみてほしいなって気持ちがあります。
あとがき
「自分の興味関心」や「自分ができること」から始まる、地域での活動
3人とも、背景やきっかけ、活動内容は多種多様ですが、共通しているのは「自分の興味関心」や「自分ができること」を大切にしているという点と、地域での活動を本当に楽しんでいるという点です。
ボランティアや市民公益活動を、地域・社会の課題やニーズから考えるのではなく、3人のように「自分の興味関心」や「自分ができること」から考えてみるというのも一つの方法だと思います。
そうすると、ボランティアや市民公益活動で大切な主体性は自然と育まれ、やりがいを持って楽しみながら活動を続けていくことができるのではないでしょうか。
この記事を読んで「地域でちょっとやってみたいことがあるかも」と思った方は、お気軽にラコルタにお越しください!
(スタッフ 住岡)
THEピックアップ
ラコルタの取り組みを紹介!
テーマカフェ
珈琲のおいしい淹れ方と自由な生き方
●開催日:7月24日(木)
NPO法人育て上げネットの宮内大志さんをゲストにお迎えし「自分の作ったもので対価を得るのが不安」という若者たちが、無料でコーヒーを提供しながら、さまざまな人や社会とつながり、働く経験を積む支援プログラムについて、その立ち上げのきっかけや想いをお話しいただきました。
当日はコーヒーの淹れ方も教えていただき、参加者同士がコーヒーを片手に、自由に交流を楽しむひとときとなりました。
写真:コーヒーでつながる時間
夏休み特別企画 市議会見学会
●開催日:8月7日(木)
議会の仕組み・議員の仕事を学び、普段はなかなか見られない議場を見学した後、「議会で話し合ってほしいこと」を考え、発表し合いました。
参加した子どもたちからは、「普段使っている公共施設も市議会で決めて作っていることを初めて知った」、「学んだことを家族や友達に伝えてあげたいなと思いました」等の感想がありました。
ご協力いただいた市議会議員やボランティアの皆さん、ありがとうございました!
写真:定員を越える44名の小学生が参加しました!
編集ノート
こんにちは。
4月に新しく入職しました小佐田です。
実は私は「eNカレッジすいた」の修了生でもあります。
そこからさまざまなつながりが広がり、今こうして、職員としてラコルタで働くことになりました。
これからは、人と人とのつながりの中から、新しいものが生まれることを応援していきたいと思っています。
(小佐田)